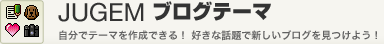- JUGEM を楽しむ
-
- 投稿する・みんなとつながる
- ブログテーマ
- ブログのお題
- その他のコンテンツ
- 芸能人・有名人のブログ
- スペシャルインタビュー
- JUGEM を楽しむ 一覧
和文化
このテーマに投稿された記事:71件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c129/25831/
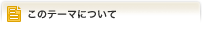
- 和文化や日本の四季に合った暮らし。
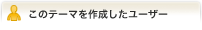
-
作者のブログへ:「otento-blog」さんのブログ
その他のテーマ:「otento-blog」さんが作成したテーマ一覧(2件)
2026年1月 清明の会体験ワークショップのご案内
2026年1月の体験ワークショップは、 *~和の心で創る初めての水引~ 「あわじ結びのポチ袋づくり」です♥ 日本の包みの文化において、和紙と水引は とても深い関係があります。^^ 水引作品づくりを通して和の心をお伝えしている 清明の会のメンバーが 水引の由来や結びの意味、紅白の意味など 丁寧にご紹介いたしますので、 和の心を深めていただけると思います。^^ ぜひご参...
和ごころ*真ごころ | 2026.01.06 Tue 00:00
2026年1月神舞体験会のご案内
新しい年を迎え、心新たにスタートするこの時に、 神舞をご一緒に体験してみませんか?^^ 舞のお稽古では、 神さまの前で舞う意識と 自然界のリズムに合わせるように呼吸をすると 自然と心と体が整ってきます。 また、丹田を意識して舞うことで 背筋も伸び、身体に一本軸が通り ものごとを前に進める意志も定まって行く感じがします。^^ 和の心に触れながら、 ...
和ごころ*真ごころ | 2026.01.05 Mon 22:49
12月の神舞体験のご案内
JUGEMテーマ:和文化 12月の神舞体験会のご案内です*^^ 先日、12月のお稽古に行ってきました。 自身の呼吸を整え、心を澄ませ みなさんの呼吸、そして自然界のリズムを 意識しながら舞の練習をすると その場がとても清々しく 神聖な空気に包まれていくのが感じられました。 手漉き和紙職人さんが 手漉きをするときは、常に雑念を祓うことを 心がけておられるとおっ...
和ごころ*真ごころ | 2025.12.08 Mon 11:59
ハギレで御朱印帳を作りました
先日から触れさせていただいていますハギレを使って 御朱印帳を作りました。 あらためてハギレの模様を見て メインの青いお花(桔梗でしょうか?)や 白とオレンジのお花は、もちろん美しいですし それぞれ使われる意味も深くて感動ですが 私は、生地に織り込まれている 地紋に、とても惹かれてしまいました。^^ 雲取り(くもどり)というのだそうです。 雲取り...
和ごころ*真ごころ | 2025.11.17 Mon 07:38
着物と和紙? 〜染色技術〜
着物のはぎれをたくさん頂きました。 渋めの色、雅な色、そこに広がる四季折々の植物…。 どのはぎれもとても素敵でわくわくします^^ 写真だけみると和紙のようにも見えませんか?^^ 和紙の種類はたくさんありますが その中でも、装飾紙や民芸紙は 写真だけですとなかなか和紙か着物かわからない時があります^^ 例えばこちら↓の和紙は、装飾紙です。 「金小...
和ごころ*真ごころ | 2025.10.29 Wed 12:00
かさね色目の和綴じ帖と御朱印帳
かさね色目を参考に御朱印帳と和綴じ帖を作ってみました。 ❖雪の下の和綴じ帖 こちらは「雪の下」のかさね色目を参考に作った和綴じ帖です。 赤、ピンク、白の雲龍染め和紙をかさねて色あわせをしてみました。 紅梅に雪が積もっている風情、伝わりますでしょうか?^^ 梅のかさねは、濃いろから薄い色をあわせるのが基本のようです。 ❖莟(つぼみ)紅梅の御朱印帳と和綴じ帖 &nb...
和ごころ*真ごころ | 2025.10.08 Wed 06:28
梅の花を愛でる
「東風吹かば 匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」 こちらは、平安時代に活躍した学問の神様で有名な藤原道真の句ですが、 万葉集や古今和歌集、枕草子などでは、 古からたくさんの梅の花が詠われています。 梅の姿そのものを詠んだり、そこに想いを託したり 梅の花だけでなく、匂いまで味わう感性がすてきだなぁと思います。 今年は暖冬ということもあり、梅の開花も例年より早かった...
和ごころ*真ごころ | 2025.10.08 Wed 06:27
「熨斗(のし)」? 〜心を包むもの〜
前回は、熨斗の起源と伊勢神宮での献上についてご紹介しました。 今回は、「心を包むもの」として折形礼法や神事に どのように息づいているのかを、ご紹介したいと思います。^^ 和紙を折って礼を形にする「折形礼法」は、 室町時代の武家礼法に端を発し、 贈答の際に「心を折り目に託す」作法として受け継がれてきました。 折形には、万葉包みや草花包みなど、 贈る...
和ごころ*真ごころ | 2025.10.01 Wed 16:22
贈り物に添える「熨斗(のし)」?
ご祝儀袋や贈り物に添える 小さな熨斗(のし)シールを作ってみました。 熨斗は日本の贈答文化において、 その起源や意味には深い背景がありますので ご紹介させていただきます。^^ 少しだけ長くなってしまうので、 2回にわけてご紹介いたします。 まずは、起源と意味から。^^ 熨斗は、もともと「熨斗鮑(のしあわび)」と呼ばれる、 干した鮑を伸...
和ごころ*真ごころ | 2025.09.30 Tue 07:39
心とからだで感じる和の心 〜神舞体験会のご案内〜
手漉き和紙の歴史を通して日本の歴史をみてみると 日本の歴史の黒子のような役割をしているのも見えて とても興味深いです。^^ 手漉きの技術は中国から渡ってきたものですが そこに自然とともに生き、四季の移り変わりを繊細に捉え、 真心をこめるという日本人ならではの精神性により 日本独自の手漉き和紙が誕生します。 この日本人ならではの、自然観、繊細な感性、 真心をこめるという精神性が、 ...
和ごころ*真ごころ | 2025.09.11 Thu 08:30
全71件中 1 - 10 件表示 (1/8 ページ)