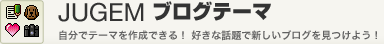- JUGEM を楽しむ
-
- 投稿する・みんなとつながる
- ブログテーマ
- ブログのお題
- その他のコンテンツ
- 芸能人・有名人のブログ
- スペシャルインタビュー
- JUGEM を楽しむ 一覧
大河ドラマ
このテーマに投稿された記事:1302件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c242/7255/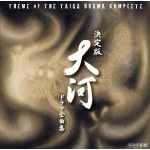
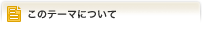
- NHK大河ドラマ
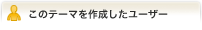
-
作者のブログへ:「bandz」さんのブログ
その他のテーマ:「bandz」さんが作成したテーマ一覧(311件)
萩紀行(26)高杉晋作草庵跡地顕彰碑
JUGEMテーマ:大河ドラマ 品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ちなどの過激な攘夷行動が、幕府からお咎めを受けると危惧した長州藩は高杉晋作を江戸から召還。 高杉は剃髪し、吉田松陰の生誕地である松本村(団子岩)に草庵を結び、東行(とうぎょう)と名乗って、十年の隠遁に入るとし、文久3年(1868)4月から藩庁に呼び出される6月までの二ヶ月の間、妻と草庵を借り、松陰の遺稿を読むなどして過ごしました。 吉田松陰と金子重輔の銅像の向かい側に、高杉晋作草庵跡地顕彰碑があります。 吉田松陰と金子重輔の銅像 ...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.16 Fri 21:38
高杉晋作寓居跡( 魚品楼跡)
JUGEMテーマ:大河ドラマ 高杉晋作が一時期住んでいた京都の白川橋の北側にあったというお茶屋・魚品楼跡。 ここには、数々の幕末の志士たちが出入りしていたそうです。 元治二年(1865)の大火で、当時の建物は焼失。その後、再建された魚品楼は、明治に入って「大まさ」という料亭になり、晋作遺愛の一部屋が保存されていたましたが、その後取り壊されてしまいました。 現在は、「とり新」という鳥料理のお店になっています。 夜は敷居が高そうなお店ですが、ランチタイムは、750円の親子丼があるそうです。 ...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.16 Fri 21:28
萩紀行(27)村田清風別宅跡
JUGEMテーマ:大河ドラマ 今日は時代を遡りますが、吉田松陰が生まれた天保期。 この時代は、百姓一揆が最も多発した時期で、長州藩は中でも、発生件数が多い藩だったといいます。天保2年には防長大一揆が起こり、周防・長門の農民10万名が参加し、紙・蝋などの藩専売廃止や年貢減免などを要求しました。 財政破たんに政治機能の麻痺など、長州藩が受けた打撃は大きく、村田清風による藩政改革のきっかけとなりました。 この清風による藩政改革によって、長州藩は財政再建に成功したといいます。 萩市平安古町に村田清風別宅...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.16 Fri 21:25
旧毛利家別邸表門(萩)
JUGEMテーマ:大河ドラマ 毛利元徳は、明治時代に、鎌倉市材木座に別邸を建てました。 明治26年(1893年)4月には英照皇太后の行啓があったそうです。 大正10(1921)年、別邸とともに毛利家萩別邸として萩市東田町に移築され、現在は、昭和49年(1974年)年に萩市堀内に移築されたこの表門のみが残っています。 なお、現在は旧毛利家別邸表門は、萩セミナーハウスの表門となっています。 桁行10.9メートル、梁間3.8メートル、棟高5.2メートル。 屋根の両端には鯱の原型と言われる鴟尾(しび)を乗せた桟瓦葺寄棟造...
大河ドラマ「花燃ゆ」「軍師官兵衛」の舞台を訪ねて | 2015.10.16 Fri 00:51
萩紀行(28)海潮寺の長井雅楽の墓
JUGEMテーマ:大河ドラマ 萩市北古萩町の海潮寺。 本堂は、藩校明倫館の遺構である聖廟を明治8(1875)年に移築し、現在もそのまま使われています。 海潮寺には、長井雅楽の墓があります。 長井雅楽時庸の墓 航海遠略策を説き、これが藩是として認められ、公武間を周旋しましたが、藩論が尊攘に転ずる中で、久坂玄瑞や木戸孝允ら尊王攘夷派により、「航海遠略策」に朝廷を誹謗する文言があると弾劾され失脚。藩命により自刃しました。 また、萩の士族救済のために、夏みかん栽培を奨励した小幡高政...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.15 Thu 23:35
久坂玄瑞が謹慎させられた法雲寺
JUGEMテーマ:大河ドラマ 縁切り祈願で有名な菊野大明神を祀る京都の法雲寺。 久坂玄瑞は、文久2年(1862)に上京し、藩論で対立していた 長井雅楽弾劾を試みましたが、この法雲寺で謹慎させられます。 この謹慎中に玄瑞が書き上げたのが、久坂は時勢論「解腕痴言」「廻瀾條議」を書き上げ、後に毛利敬親に認められ、長井雅楽を失脚に追い込むことになりました。 ここから少し南に下ったところに、当時の長州藩邸(現・京都ホテルオークラ)があります。
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.15 Thu 23:25
山口藩庁門〜山口旧県庁舎〜旧県会議事堂
JUGEMテーマ:大河ドラマ 1863年(文久3)藩主・毛利敬親は、萩から山口へ拠点を移し、中河原御茶屋で政務を執っていましたが、今の県庁の位置に藩庁の移転を計画し、翌年の元治元年(1864)から御屋形とよばれる居館をここに築き始め、慶応3年(1867)に竣工しました。 幕府に対しては、「山口の政庁は城ではない」と伝えてはいましたが、実際は、天然の要塞となる山に囲まれ、砲台や水濠などを備えた城郭で、当時としては最先端の西洋式八稜城郭でした。 坂本龍馬が、西郷隆盛との面談が失敗して怒って帰った桂小五郎を呼び出し...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.15 Thu 11:51
前橋城跡
JUGEMテーマ:大河ドラマ 前橋城は、群馬県の前橋台地北東縁に築かれた平城で、古くは厩橋城(まやばしじょう)と呼ばれ、また関東七名城の一つに数えられました。 明治9年(1876)熊谷県から群馬県になった時、県庁は高崎に置かれましたが、旧高崎城に、陸軍省の兵営があり、手狭になったため、楫取素彦は、県庁を前橋に移しました。 本丸跡地には、群馬県庁本庁舎、二の丸跡地には前橋市役所、三の丸跡地は前橋地方裁判所、前橋公園となり、遺構として、土塁、車橋門跡などが残されています。 ...
大河ドラマ「花燃ゆ」「軍師官兵衛」の舞台を訪ねて | 2015.10.14 Wed 11:00
前橋城跡
JUGEMテーマ:大河ドラマ 前橋城は、群馬県の前橋台地北東縁に築かれた平城で、古くは厩橋城(まやばしじょう)と呼ばれ、また関東七名城の一つに数えられました。 明治9年(1876)熊谷県から群馬県になった時、県庁は高崎に置かれましたが、旧高崎城に、陸軍省の兵営があり、手狭になったため、楫取素彦は、県庁を前橋に移しました。 本丸跡地には、群馬県庁本庁舎、二の丸跡地には前橋市役所、三の丸跡地は前橋地方裁判所、前橋公園となり、遺構として、土塁、車橋門跡などが残されています。 ...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.14 Wed 10:54
七卿落ち(4)三田尻御茶屋 英雲荘
JUGEMテーマ:大河ドラマ 三田尻は、萩城下唐樋から三田尻御茶屋まで続く萩往還の終点であり、大名の参勤交代の道として整備され、多くの人々に利用されました。 三田尻御茶屋(みたじりおちゃや)は、江戸時代、承応3年(1654)萩藩2代藩主・毛利綱広によって建てられた長州藩の公館で、藩主の参勤交代や領内巡視時の休憩、また迎賓に使われていました。 7代藩主の重就は、家督を譲って隠居した翌年の1783年(天明3年)に大規模な改築を行い、大観楼などの建設を行いました。改修後に重就は三田尻御茶屋へ移住して、晩年の6...
大河ドラマを追いかけて | 2015.10.13 Tue 11:55
全1000件中 951 - 960 件表示 (96/100 ページ)