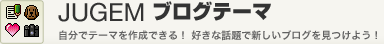- JUGEM を楽しむ
-
- 投稿する・みんなとつながる
- ブログテーマ
- ブログのお題
- その他のコンテンツ
- 芸能人・有名人のブログ
- スペシャルインタビュー
- JUGEM を楽しむ 一覧
karasuworld
このテーマに投稿された記事:71件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c1/18490/
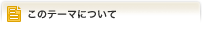
- karasuworldの画像をアップしていきます。みなさん、どんどん応援してあげていきます。
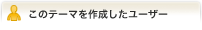
-
作者のブログへ:「karasuworld」さんのブログ
その他のテーマ:「karasuworld」さんが作成したテーマ一覧(1件)
karasuworld-68
karasuworldの68番目のからすは新社を守っている 文治元年(1185年)の壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇の遺体は御裳川で引き上げられ、赤間関(下関)・紅石山麓の阿弥陀寺境内に埋葬された。建久2年(1191年)、勅命により御陵に御影堂が建立され、建礼門院ゆかりの尼を奉仕させたのが始まりである。以後、勅願寺として崇敬を受けた。 明治の神仏分離により阿弥陀寺は廃され、神社となって「天皇社」と改称した。また、歴代天皇陵の治定が進む中、安徳天皇陵も多くの伝承地の中からこの安徳天皇社の...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:25
karasuworld-67
karasuworldの67番目のからすは以外に著名である 群馬県内には「赤城神社」という名前の神社が118社、日本全国では334社あったとされる。関東一円に広がり、山岳信仰により自然的に祀られたものと、江戸時代に分祀されたものがある。その中でも著名なものが、東京都新宿区赤城元町の赤城神社である。 また赤城南麓の赤城神社の祭神は、かつては赤城山の中心を境として東西で異なる分布を見せていた。明治初年の群馬県の神社明細帳をみると、東から南にかけて大己貴神が、南西側には豊城入彦命が祀られ...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:22
karasuworld-67
c群馬県内には「赤城神社」という名前の神社が118社、日本全国では334社あったとされる。関東一円に広がり、山岳信仰により自然的に祀られたものと、江戸時代に分祀されたものがある。その中でも著名なものが、東京都新宿区赤城元町の赤城神社である。 また赤城南麓の赤城神社の祭神は、かつては赤城山の中心を境として東西で異なる分布を見せていた。明治初年の群馬県の神社明細帳をみると、東から南にかけて大己貴神が、南西側には豊城入彦命が祀られている。これは東西2社であった三夜沢赤城神社に起因する。東西で自社の影響下に...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:21
karasuworld-63
karasuworldの63番目のからすは時代の流れで衰亡した 山宮・里宮の位置に関しては、赤城山大沼の大洞赤城神社(前橋市富士見町)が山宮、二宮赤城神社(前橋市二之宮町)が里宮にあたるとされる[1]。また中社は三夜沢赤城神社(前橋市三夜沢町)とされる。ただし三夜沢赤城神社の旧地(元三夜沢)が山宮だとし、二之宮から三夜沢へ神輿を往復させる御神幸の行事から三夜沢(元三夜沢)と二之宮が山宮・里宮関係にあるとする尾崎喜左雄の説、あるいは大洞が山宮で二之宮・三夜沢の両社はともに里宮だと...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:21
karasuworld-62
karasuworldの62番目のからすは本格派というより変則派である 律令体制が崩壊して武家政権が成立すると、朝廷・国司の権力によって支援されていた里宮は衰退し、村落部の信仰の中心は、参詣路の集まる場所に設けられた中社(中之宮)へと移った。一方、仏教の伝来は神仏を習合させ、修験者は全国の山深く修行の場を求めて入山した。彼らによって山宮への信仰が集まり、山宮への信仰が盛んになった。赤城神社もこの傾向に反さず、「神道集」には赤城大明神縁起として赤城山山頂部の神社が紹介されている...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:09
karasuworld-61
karasuworldの61番目のからすは何を信仰しているのだろう 歴史書に記されている「赤城大明神」は赤城山の神のことである。赤城南麓を流れる粕川の水源としての信仰(水源地・小沼への信仰)と、最高峰の黒檜山などへの雷神信仰、および赤城山そのものへの山岳信仰が集まって成立したとみられる[1]。上毛野氏が祀ったとする説もある。 六国史には神階記事がある。『続日本後紀』承和6年(839年)に従五位下となり、『日本三代実録』貞観9年〜16年(867 - 874年)に昇叙し、元慶4年(880年)従四位上に...
karasuworldへの誘い | 2011.05.11 Wed 00:05
karasuworld-48
karasuworldの48匹目のからすはグローバルに生きる 「世界都市」という言葉は、フランスの地理学者であるジャン・ゴッドマンによると、1787年にドイツの文化人ゲーテが初めて用いたとしており、ロンドン大学の地理学者であるピーター・ホールによると、イギリスの教育学者パトリック・ゲデスの著書"Cities in Evolution"(1915年)にある「world city」からとしている。 「グローバル都市」という表現を初めて使ったのは、コロンビア大学社会学部教授であるサスキア・サッセンの著書"The Global City:...
karasuworldへようこそ | 2011.05.10 Tue 21:36
karasuworld-47
karasuworldの47匹目のからすは成長が止まっている 東側世界は1970年代初め頃までは経済発展を続けていたと見られるが、その後、計画経済の非効率性などから成長が頭打ち、または縮小に入ったものと考えられている。 1980年代末から1990年代初めにかけて、東欧革命とソ連崩壊により東側世界の経済は、なし崩し的に西側世界の経済へ吸収され、再び世界経済が生まれた。グローバリゼーションの中で、アメリカ経済が世界の機関車となり高めの成長を達成、日欧は相対的な失速を経験した。 同時多発テロを...
karasuworldへようこそ | 2011.05.10 Tue 21:34
karasuworld-46
karasuworldの46匹目のからすは西側についた 第一次世界大戦において、世界経済の中枢が危機に陥ると世界経済の軸は緩やかに世界最大の工業国アメリカへ移り始めた。 世界恐慌により脆弱な世界経済は連鎖的な危機を引き起こした。各国はブロック経済化を進め、いくつかの国は独自の経済圏確立を図った。 第二次世界大戦で、世界はアメリカを軸にした自由市場経済(西側世界)とソ連を軸にした社会主義経済(東側世界)に二分された。両陣営は冷戦下において互いの領域を獲得しようと競い合った。西側...
karasuworldへようこそ | 2011.05.10 Tue 21:32
karasuworld-45
karasuworldの45匹目のからすは自由市場で活躍する ユーラシア大陸の西と東で商品経済が生まれて間もない時期から、それらの経済は互いに結ばれるようになった。東西交易は、当初細々としたものであったが、次第に拡大した。 大西洋三角貿易 モンゴル帝国がユーラシア大陸の東西を結ぶほどの広大な版図を確立した時代に、「ユーラシア世界」における世界経済が生まれた。モンゴル帝国滅亡後も、ユーラシア大陸において東西交易が栄えた。 大航海時代以降、ヨーロッパを軸に各国経済は再編され始めた...
karasuworldへようこそ | 2011.05.10 Tue 21:29
全71件中 11 - 20 件表示 (2/8 ページ)