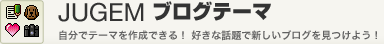- JUGEM を楽しむ
-
- 投稿する・みんなとつながる
- ブログテーマ
- ブログのお題
- その他のコンテンツ
- 芸能人・有名人のブログ
- スペシャルインタビュー
- JUGEM を楽しむ 一覧
コーヒー
このテーマに投稿された記事:581件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c137/9248/
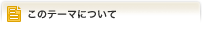
-
コーヒーを飲むこと。
コーヒーを焙煎すること。
コーヒーのあるお店探検。
コーヒーに関する様々なこと。 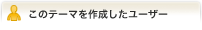
-
作者のブログへ:「dis-coffee」さんのブログ
その他のテーマ:「dis-coffee」さんが作成したテーマ一覧(1件)
「コーヒーは飲むものか」 その2
JUGEMテーマ:コーヒー (2) コーヒーは飲むもの 「あの頃の自分の事」(芥川龍之介) 『その後で「君はどうした」と訊くから、「やつと『鼻』を半分ばかり書いた」と答へた。成瀬も今年の夏、日本アルプスへ行つた時の話を書きかけてゐると云ふ事だつた。それから三人で、久米の拵へた珈琲(コオヒイ)を【飲みながら】、創作上の話を長い間した。』 「しるこ」(芥川龍之介) 『久保田万太郎君の「しるこ」のことを書いてゐるのを見、僕も亦「しるこ」のことを書いて見たい欲望を感じた・・・それも「常盤」の...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:48
「コーヒーは飲むものか」 その1
JUGEMテーマ:コーヒー コーヒーを飲むことをどのように表現するのでしょうか。コーヒーは「飲む」のに決まっていると思っていましたがそれだけではなさそうです。コーヒーを「啜るもの、飲むもの、含むもの、味わうもの、たしなむもの」などいろいろな表現があることを、いくつかの文学作品で調べてみました。表現を強調するために【 】で括っています。 (1) コーヒーは啜(すす)るもの 「C先生への手紙」(宮本百合子 ) 『薔薇液を身に浴び、華奢な寛衣(ネグリジェー)をまとい、寝起きの珈琲を【啜り】な...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:45
「コーヒーをカップに注ぐことを何というのか」 その2
JUGEMテーマ:コーヒー (3) コーヒーは酌むもの 「根岸庵を訪う記」(寺田寅彦) 『絵とちがって鋳物だから蝸牛が大変よく利いているとか云うて不折もよほど気に入った様子だった。羽織を質入れしてもぜひ拵えさせると云うていたそうだと。話し半ば老母が珈琲を【酌んで】来る。子規には牛乳を持って来た。・・・』 (4) コーヒーは煮るもの 「平塚・山川・山田三女史に答う」(与謝野晶子) 『食事は路すがら麺麭パンと冷し肉ぐらいを買って来るのですから、唯だ瓦斯ガスで珈琲を【煮る】だけで簡単に済まされ...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:43
「コーヒーをカップに注ぐことを何というのか」 その1
JUGEMテーマ:コーヒー コーヒーをカップに注ぐ行為を何というかに、いろいろな表現がありますが、国内の文学作品でどのように表現しているのでしょうか。いうまでもなく、すべての作品を調べるわけにいきませんのでそのうちのいくつかについてを列挙してみます。表現を強調するため関係文字を【 】で括っています。 (1) コーヒーは淹れるもの 「おばあさん」(ささきふさ) 『「まだまる四十年も生きなくちやならないんだよ、君。」と彼は訪ねてきた社の人に云つた。「君はあと五十年か、ハハ。それも大人にな...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:40
「天災は忘れた頃にやってくる」その5
JUGEMテーマ:コーヒー コーヒーと哲学、宗教の類似性について次のように記しています。 「…自分にとってはマーブルの卓上におかれた一杯のコーヒーは自分のための哲学であり宗教であり芸術であると言ってもいいかもしれない。これによって自分の本然の仕事がいくぶんでも能率を上げることができれば、少なくも自身にとっては下手な芸術や半熟の哲学や生ぬるい宗教よりもプラグマティックなものである。ただあまりに安価で外聞の悪い意地のきたない原動力ではないかと言われればそのとおりである。しかしこういうも...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:38
「天災は忘れた頃にやってくる」その4
JUGEMテーマ:コーヒー コーヒーを飲むことの意味や自覚していた効用について次のような文を残しています。 コーヒーは飲むために飲むのではない 『しかし自分がコーヒーを飲むのは、どうもコーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではないように思われる。宅の台所で骨を折ってせいぜいうまく出したコーヒーを、引き散らかした居間の書卓の上で味わうのではどうも何か物足らなくて、コーヒーを飲んだ気になりかねる。やはり人造でもマーブルか、乳色ガラスのテーブルの上に銀器が光っていて、一輪のカーネーションでも...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:36
「天災は忘れた頃にやってくる」その3
JUGEMテーマ:コーヒー 外遊中のコーヒーとのつきあい 『スカンディナヴィアの田舎には恐ろしくがんじょうで分厚でたたきつけても割れそうもないコーヒー茶わんにしばしば出会った。そうして茶わんの縁の厚みでコーヒーの味覚に差違を感ずるという興味ある事実を体験した。ロシア人の発音するコーフイが日本流によく似ている事を知った。 …自分の出会った限りのロンドンのコーヒーは多くはまずかった。大概の場合はABCやライオンの民衆的なる紅茶で我慢するほかはなかった。英国人が常識的健全なのは紅茶ば...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:33
「天災は忘れた頃にやってくる」その2
JUGEMテーマ:コーヒー 寅彦が出会ったコーヒー 寅彦は明治11年(1878年)生まれ。寅彦が幼い時の記憶に次のようなものがあります。 「八、九歳のころ医者の命令で始めて牛乳というものを飲まされた。当時まだ牛乳は少なくとも大衆一般の嗜好品でもなく、常用栄養品でもなく、主として病弱な人間の薬用品であったように見える。そうして、牛乳やいわゆるソップがどうにも臭くって飲めず、飲めばきっと嘔吐したり下痢したりするという古風な趣味の人の多かったころであった。 …始めて飲んだ牛乳はやはり飲み...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:31
「天災は忘れた頃にやってくる」その1
JUGEMテーマ:コーヒー 「天災は忘れた頃にやってくる」のか ことしも地震、台風、竜巻、洪水など未曾有の災害が起こり多数の被害がありました。「天災は忘れた頃にやって来る」という言葉を聞きますが、最近は「天災は忘れずにやってくる」という方が実情に合っているようです。 その「天災は忘れた頃にやって来る」という言葉は物理学者・随筆家である寺田寅彦(1878年・明治11年 - 1935・昭和10年)のものとされていますが、寺田寅彦の著書にその言葉は残されていません。ではどこから出たのでしょうか。 寺...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:26
「可否道」その10
JUGEMテーマ:コーヒー 野点(のだて)のコーヒー モエ子と菅を一緒にさせる算段をした可否会の会員は,野火止めの「平泉寺」(現実には平林寺?)のコーヒーの野点に出向きました。 コーヒー沸かしを忘れてしまったため「山賊風」でコーヒーをいれました。「山賊風」のいれかたとは次のようなものです。 「沸いた湯に粗挽きのモカ,コロンビア,ブラジルの豆を投入。間もなく火山の溶岩のような色と形状を示してむくむくと盛り上がってくると,こたえられない芳香が鼻を打つ。茶褐色の細かい泡が正に吹きこぼれる汐...
コーヒー談話室 | 2015.05.21 Thu 17:23
全581件中 261 - 270 件表示 (27/59 ページ)