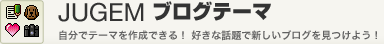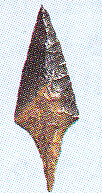- JUGEM を楽しむ
-
- 投稿する・みんなとつながる
- ブログテーマ
- ブログのお題
- その他のコンテンツ
- 芸能人・有名人のブログ
- スペシャルインタビュー
- JUGEM を楽しむ 一覧
日本史
このテーマに投稿された記事:161件 | このテーマのURL:https://jugem.jp/theme/c43/6470/
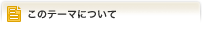
- 日本史に少しでも関係のあるテーマならOKです。時代を問わず投稿しましょう。
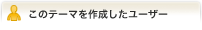
-
作者のブログへ:「histons」さんのブログ
その他のテーマ:「histons」さんが作成したテーマ一覧(1件)
磨製石器の発見は日本が最古‐日本文明の謎に迫る
日本の国に生まれて良かったと思える一冊です。 日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか【電子書籍】[ 竹田恒泰 ] 価格:650円 (2017/1/3時点) JUGEMテーマ:日本史 磨製石器の発見は日本が最古‐日本文明の謎に迫る 磨製石器とは、人間の手によって加工された石器である。 世界では約2万5千年前の磨製石器が発見さ...
教科書に載らない歴史ブログ!英雄や事件の真実に迫る教育実践 | 2016.10.19 Wed 17:38
宇和島 鶴瓶の家族に乾杯 うどん屋さん
たまたまテレビを点けたら、NHKで「鶴瓶の家族に乾杯」が宇和島SPでした。そして見覚えのあるうどん屋さんが登場。私もおいしくて何度か朝に食べに行きました。看板もなく、冬なんか表の戸も閉まっているので、本当にこの「家」なんだろうかという感じで最初は入りました。冬でも暖房も点けず、ほとんど江戸時代の生活に電灯とガスだけあるような感じがまた素晴らしい。味もよく、安くてお勧めです。
蒔絵・研究日誌 | 2016.08.29 Mon 22:03
織田信長は実は生きていた?実は生きていたシリーズ
JUGEMテーマ:日本史 織田信長は実は生きていた? |『本能寺の変』 1582年6月2日、本能寺にて、明智光秀に討たれて、その生涯を閉じる。 |『俗説』 ・織田信長は本能寺を逃れて生きていた。 ・本能寺から逃れたが、その後、逃げる途中で息絶えた。 ・豊臣秀吉に幽閉されていた。 |『検証』 ・織田信長の遺体が発見されていない。 マン...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.08.04 Thu 20:13
榊原康政、徳川内紛の危機を防いだその活躍とは?徳川四天王編
JUGEMテーマ:日本史 榊原康政、徳川内紛の危機を防いだその活躍とは?徳川四天王編 「人物」 徳川家康の側近、武勇に優れ徳川四天王と呼ばれた。後に館林藩主に。 「最大の功績」 榊原康正は関ヶ原の合戦時に、徳川秀忠軍と行動を共にした。 →しかし、徳川秀忠軍は関ヶ原の合戦に間に合わず、遅参すると言う大失態を犯してしまう。 徳川家康は大激怒し、秀忠は弁明のために家康に会おうとするが、家康は拒否。 ...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.07.25 Mon 18:22
豊臣秀吉、極悪非道と正義の味方
JUGEMテーマ:日本史 豊臣秀吉、極悪非道と正義の味方 「極悪非道」 豊臣秀吉と言えば、大恩ある織田家を乗っ取る。 自分の悪口を書かれた程度で関係ない人まで虐殺するなど、その極悪非道ぶりは有名である。 「正義の味方」 戦国時代、大量の日本人女性が奴隷としてポルトガル宣教師によって世界へ売られていた。 この様子を嘆いた秀吉は、後のバテレン追放令を出...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.07.04 Mon 20:03
聖徳太子は本当に実在したのか?
JUGEMテーマ:日本史 聖徳太子は本当に実在したのか? 聖徳太子と言えば、教科書にも必ず登場する日本史を代表す人物。 しかし、近年その存在に異議を唱える説が。 「聖徳太子不在論」 ・聖徳太子の誕生伝説がキリストや釈迦の伝説に似ている。 ・「日出づる処の天子」で始まる有名な外交文書は日本書記に記述されておらず、隋書に書かれた名前も聖徳太子でない可能性がある。 ・聖徳太子の記述が人間離れ...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.06.24 Fri 08:21
西郷隆盛にも生存説 実は生きていたシリーズ
西郷隆盛にも生存説 実は生きていたシリーズ 「通説」 西郷隆盛は西南戦争に敗れて自害した。 「俗説」 西郷隆盛は生き延びてロシアに渡った。 ロシア皇帝ニコライが来日する時に一緒に日本へやって来ると噂が流れた。 「検証及び大津事件」 ・西南戦争後、西郷隆盛の遺体が、どれかはっきりと分からなかった。 西郷隆盛の顔を知っている人がほとんどいない。 ・西郷隆盛生存説が大津事件を引き起こした。 ...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.06.17 Fri 07:29
坂本龍馬の活動資金の裏事情とは
JUGEMテーマ:日本史 ●次の記事へ(総合案内・他記事はここから検索できます。) 坂本龍馬の活動資金の裏事情とは 「疑問」 坂本龍馬と言えば、全国各地で精力的に活動をしていた事で有名。 さぞお金が必要であっただろう。そのお金は何処から出ていたのだろうか疑問が残る。 「お金根の出所」 坂本龍馬にお金を供給していた人は誰なのか様々な説が飛び交っている。 坂本龍馬にはた...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.06.06 Mon 17:12
日本人奴隷、衝撃の事実を紹介、歴史の闇の部分を探る、教科書で語りたい歴史
JUGEMテーマ:日本史 日本人奴隷、衝撃の事実を紹介、歴史の闇の部分を探る、教科書で語りたい歴史 奴隷貿易、日本とは関係がない遠い国の話の様に思うが、かつて大量の日本人が奴隷として、外国に売られていた時代がある。 時は戦国時代、火縄銃の需要が高まり、ポルトガル商人や宣教師達が多数日本にやってきた。 ポルトガルの目的はキリスト教の布教だけではなく、日本でお金儲けをする事であった。 火縄銃や火薬を売買するだけでなく、日本人を奴隷として購入して、外国に売り飛ばして...
教科書に載らない歴史の真相に迫る教育実践 | 2016.04.22 Fri 20:28
全161件中 81 - 90 件表示 (9/17 ページ)